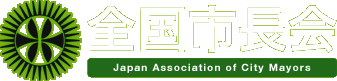全国市長会の主張 -要望-H16.11
|
介護保険制度に関する要望
介護保険制度の円滑な運営を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。 1.財政運営について
また、制度変更に伴う財政影響については、国の責任において措置すること。 (2) 介護給付費負担金については、各保険者に対し給付費の25%を確実に配分し、現行の調整交付金は別枠化すること。 また、国等の法定負担分は、安定的な事業運営の観点から、年度内に確実に交付すること。 なお、調整交付金の算定を暦年単位から年度単位とするなど、個々の市町村の執行実績に見合った交付とすること。 (3) 財政安定化基金の原資については、国及び都道府県の負担とすること。 (4) 制度の見直しに伴って生ずる介護予防、要介護認定及び電算システムの改修等経費のほか、保険料未納者対策等の事務経費について、十分な財政措置を講じること。 (5) 市町村介護保険事業計画の見直しに係る経費について、財政措置を講じること。
(2) 重度心身障害者については、医療系サービスの必要度が高く、介護保険利用者負担が高額になるため、国の負担により減免措置を講じること。
(2) 高齢者ができるだけ要介護状態にならないようにするために必要な介護予防や生きがい活動に係る諸施策の充実を図るとともに、介護予防拠点の整備に対する必要な財政措置を講じること。 (3) 軽度要介護者に対する自立支援や重度化の防止に向けた介護予防サービスの提供を積極的に行うことが重要であることから、介護予防サービスのあり方、同サービスに係る人材の確保・育成、事業者のサービス提供体制を含め、早急に、より適切なサービスが提供されるようにすること。
(2) 現行の第1号保険料の区分については、第2段階の対象者における収入の格差が大きく、所得の低い者にとって負担が大きいので、住民の所得状況に応じた多段階制の採用等、よりきめ細かい保険料段階区分を設定すること。 (3) 保険料納付の利便性、徴収事務の効率化及び収納率の向上を図るため、全ての年金を特別徴収の対象とすること。 また、年度途中での資格取得や徴収額変更について、速やかに特別徴収ができるようにするなど、特別徴収事務処理の迅速化を図るとともに、被保険者が理解しやすいよう所要の措置を講じること。
(2) 主治医意見書の作成手数料の支払にあたって、居宅・施設入所の別及び新規・継続の別により複雑な確認事務が必要となっているため、その見直しを行うこと。 また、要介護(支援)認定を30日以内に行えるよう、主治医意見書の迅速な作成を促すべく必要な対策を講じること。
(2) 都道府県が有料老人ホーム等の特定施設やグループホームを指定するにあたり、高齢者保健福祉計画及び市町村介護保険事業計画との整合性が図られるよう、事前に保険者である市町村と協議する仕組みを確立すること。 (3) 現時点において、都道府県におけるサービス事業者に対する指導・監督が十分に行われているとは言い難いことから、その機能強化を図るとともに、サービスの質の確保、利用者保護の重要性等にかんがみ、都道府県と同程度の調査権限を保険者にも付与し、都道府県と保険者である市町村とが連携する仕組みを確立すること。 (4) 保険給付及びサービス提供の適正化が図られるよう、ケアマネジャーが居宅サービス事業所から独立した立場でケアプランを作成できる環境づくりなど、ケアマネジャーの中立性・公平性を更に確保するための具体的な対策を講じること。 被保険者の範囲の拡大については、引き続き慎重に検討するとともに、障害者施策との統合については、今回の介護保険制度の見直しにおいて絶対に行わないこと。 8.その他
(2) 介護保険制度の見直しにあたり、市町村と十分協議するとともに、制度変更にあたっては、速やかに情報提供を行うこと。 (3) 被保険者証の有効期限を定めないことや高額介護サービス費に係る申請手続きの自動償還払い化など、利用者の利便性や事務の効率化・簡素化を図る方策について、市町村が独自の判断で行えるようにすること。 (4) 介護保険制度の見直しや保険料・利用料等に関する広報を、国民にわかりやすい内容でこれまで以上に積極的に行うこと。 (5) 介護費用適正化緊急対策事業の充実を図ること。 (6) 養護老人ホームのあり方について所要の検討を行うこと。 (7) 利用者負担(利用料)について、介護費用控除を創設すること。 以上要望する。 |